読んでいただけるメニューブックを
 その、最大の武器であるメニューブックは、ある程度大判で、しかもきれいな印刷物であることが望ましい。それは、見やすいこと・わかりやすいことと、好い印象を与えることを満たしたいからである。そしてそれは、「読んで」もらえるメニューブックであるということである。 その、最大の武器であるメニューブックは、ある程度大判で、しかもきれいな印刷物であることが望ましい。それは、見やすいこと・わかりやすいことと、好い印象を与えることを満たしたいからである。そしてそれは、「読んで」もらえるメニューブックであるということである。
メニューブックは、素人が作ると、手描きの、いかにも素人っぽいものしかできない。伝えたい情報はどうにか伝わるかもしれないが、最低限でしかないことが多く、なにより見栄えの点で、どうしてもプロ制作のものに劣る。最近はコンピューターの普及で描画ソフトなどもあるにはあるが使いこなすのがたいへんで、仕上がりもやはり素人っぽさは拭えず、とにかく「一生懸命作った」ことはわかる、という程度のでき上がりだ。そこで、見栄え・完成度を意識するとなると、プロ(制作会社)に任せることになる。プロに依頼すれば写真やイラストを駆使した見栄えのするデザインとなり、いかにも「プロのお店」らしいメニューを作り上げることができる。
ただ、プロに依頼すると、時間と経費がかかる。洗車メニューを作った経験がある制作会社であれば雛型も用意できるだろうし、要点を理解しているので、速い対応と適切な価格設定は可能だろうが、そういう制作会社は極めて少ないし、やはりそれなりに高価である。まして新商品や季節商品など、細かい手直しを必要としたり、新しいページを作成する機会が多ければ多いほど、費用がかかるし、手間もかかる。
何とかならないものだろうか。
プロの品質をお手許で…、がミソ
そういう悩みを一挙に解決しようと言うのが、コンピューターによる洗車・コーティングメニュー作成ソフト「キーパー・メニュービルダー」である。一番のメリットは、プロのデザインによるメニューが手許で印刷できる、ということ。
キーパーメニュービルダーは、あらかじめデザインされているメニューページが12分類あり、そのうちのいくつかは3パターンのバリエーションを持ち、しかもそれぞれに車種料金の設定が3・4・5車種あるので、67パターンのメニューを自由に組み合わせて印刷することができる。
内容は自由自在に編集できる
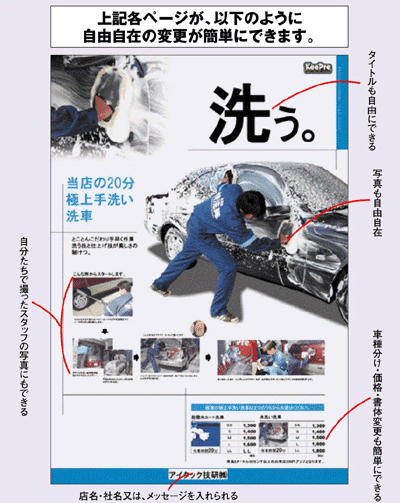 しかも、それぞれのページの写真や図版を、あらかじめ組み込まれているものとは別のものに変更することができる。たとえば、自社スタッフが洗車したりキーパー施工をしているシーンをデジカメで撮影し、その写真をメニューページに使用することができる仕組みになっている。 しかも、それぞれのページの写真や図版を、あらかじめ組み込まれているものとは別のものに変更することができる。たとえば、自社スタッフが洗車したりキーパー施工をしているシーンをデジカメで撮影し、その写真をメニューページに使用することができる仕組みになっている。
変更・編集できる項目は、
- 車種分類名(SS・S・M・L・LLや軽・小型・普通・中型・大型・ワンボックスなどの表現)
- 車種分類ごとの料金
- 会社(SS)名
- ページのタイトルとサブタイトル
- ページの案内文
- 商品名
- 商品説明
- 写真や図版
で、それぞれページごとに変更できる。タイトルや文字は、書体・文字の大きさ・色などを変更できる。パソコンにインストールしてある書体数が多ければ、変わった書体・目立つ書体を使える要になる。
ページ内文章の変更もできるので、お店ごとの独自の表現で商品を説明したいときなどに活用してほしい。
前述したように、写真や図・イラストも、あらかじめ準備してある写真から選んで変更できるばかりでなく、デジカメで撮影したオリジナル写真を使うこともできる。ユニフォームなどが気になるのであれば、早速写真を写してみるのも良いだろう。
ページの台紙以外は自由に編集できるため、ソフトの扱いに慣れれば、お店ごとに独自なページを作ることもできる。もちろんそんな面倒なことは嫌だ、というのであれば、初期デザインのまま車種ごとの設定料金だけ変えて印刷すれば良い。簡単派もオリジナル派も、どちらも満足できるソフトウェアである。
A4判もB4判も、どちらも印刷できる
メニューの印刷は、A4判もB4判もどちらも印刷できる。
メニューの判りやすさや視覚効果からいえば、やはり大判であるB4判が中心になるだろうが、ゲストルームのテーブルで扱いやすくこざっぱりしたものを求めるという点で小さいA4判を好むお店もあるだろう。
キーパー・メニュービルダーは、そのどちらも印刷できる。印刷機は、レーザープリンターでもインクジェットプリンターでも、どちらでも使える。ただし、インクジェットプリンターでB4判を印刷できるものは少ない。ご使用の環境に合わせて印刷サイズを選んでいただくことになる。
メニュー説明はセリフを作ろう
ゲストルームに招き入れ、キーパー・メニュービルダーで作ったメニューブックをご覧いただき、それで商品をご注文いただくわけだが、初めてのお客様にはこれだけでは説明不足。メニューブックの内容を耳からもご理解いただくことが必要だ。
メニューブックの配列に従って説明すれば良いのだが、やはり判りやすく、なおかつメリハリをつけた説明が好もしい。そのためには行き当たりばったりでは無く、標準となるメニュー説明の台詞を作り、それを暗誦できるまできちんと覚えて、お客様に対して説明するようにしたいものである。
さらにもう一歩進んで、メニューを説明するときの仕種も大切なこと。説明している内容を指し示しながら表情豊かに案内できれば、受注率の向上につながるだろう。
ご提供方法、発売時期など、現在検討中です。
次号以降で発表します。ご期待下さい。 |
